発生ゲノミクス研究グループ
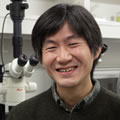
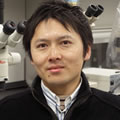
- 准教授 :
- 荻野 肇
- 助教 :
- 越智 陽城
- E-mail :
- { ogino,harukiochi }@bs.naist.jp
- 研究室HP :
- http://bsgcoe.naist.jp/ogino/index.html

図1 ツメガエル(ゼノパス•トロピカリス)における、メガヌクレアーゼ I–SceI を用いた高効率トランスジェネシス

図2 Six3 遺伝子のエンハンサーの制御下で発現するレポーター遺伝子を導入したカエル原腸胚。予定前脳及び眼領域にレポーター遺伝子の発現がみられる(紫色)。
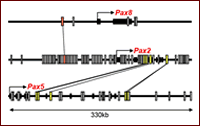
図3 ヒト Pax2/5/8 パラロググループの遺伝子座周辺に散在するCNE。赤と黄色はパラログ間で保存されているCNEを示す。
研究・教育の概要
近年、サカナからヒトに至るまで、それら脊椎動物のゲノム中に保存されている非コード配列(Conserved non-coding elements; CNE)の多くが、発生制御遺伝子の発現をコントロールする調節配列(エンハンサー)であることが明らかになってきました。それゆえ、CNEの機能の解析は、脊椎動物の発生を支配する種を超えた普遍的な遺伝子ネットワークの解明につながると考えられます。また、CNEのエンハンサー活性は、相同なものどうしであっても種間で異なる場合があり、それらの機能解析は脊椎動物のかたちの多様性の不思議を解く糸口にもなります。私達のグループは頭部及び腎臓の形成を支配する遺伝子群に注目し、その発現を調節するCNEの機能をカエルのトランスジェニックシステムを用いて研究しています。
主な研究テーマ
- 1) 前脳と眼の形成メカニズム
- 脊椎動物の予定前脳および眼領域は、原腸陥入時にオーガナイザーからの誘導シグナルによって形成されます。Wnt阻害因子やBMP阻害因子などがそのシグナルの実体として同定されていますが、それらがどのようにして頭部形成遺伝子群の転写を活性化するのか、そのメカニズムは未だよくわかっていません。私達は頭部形成遺伝子群の発現を調節するCNEの機能解析からこの問題にアプローチしています。また、終脳や眼の大きさはサカナからヒトまで大きく異なりますが、これら形態的な種差とCNEのエンハンサー活性の種差についても解析しています。
- 2) ゲノム重複にともなうシス調節機構の進化の解析
- 脊椎動物は進化の過程でゲノムの重複により、様々な発生制御遺伝子についてパラロググループを形成してきました。同じパラロググループに属する遺伝子の中には、その発現パターンが一部重複するものがあり、それらにおいてはシス調節機構が部分的に保存されていると考えられます。進化にともなうシス調節機構の多様化のメカニズム、または多様化を制限する要因を解明するため、眼と感覚器プラコード•腎臓の発生に関与するパラロググループに注目して、そのCNEの機能解析をおこなっています。
主な発表論文・著作
- Sato, S., et al., Dev. Biol., 344, 158-171, 2010
- Hellsten, U., et al., Science, 328, 633-636, 2010
- Kurokawa, D., et al., Dev. Biol., 342, 110-120, 2010
- Ochi H. & Westerfield M., BMC Dev. Biol., 9, 13, 2009
- Ogino H. & Ochi H., Dev. Growth Differ., 51, 387-401, 2009
- Sakamoto K., et al., PloS One, 4(4), e5121, 2009
- Ogino H., et al., Development, 135, 249-258, 2008
- Ochi H. et al., J. Biol. Chem., 283, 3539-3536, 2008
- Yokoyama H., et al., Dev. Biol., 306, 170-178, 2007
- Ochi H. & Westerfield M., Dev. Growth Differ., 49, 1-11, 2007
- Ogino H., et al., Nature Protocol, 1, 1703-1710, 2006
- Ogino H., et al., Mech. Dev., 123, 103-113, 2006
- Ochi H., et al., Dev. Biol., 297, 127-140, 2006
- Hirsh N., et al., Dev. Dyn., 225, 522-535, 2003
- Ochi H., et al., J. Biol. Chem., 278, 537-544, 2003
- Ogino H. & Yasuda K., Dev. Growth Differ., 42, 437-448, 2000
- Ogino H. & Yasuda K., Science, 280, 115-118, 1998
